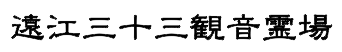第三十一番 紅梅山 菊水寺
- 宗派
- 曹洞宗
- ご本尊
- 千手千眼観世音菩薩(寄木造り・立像・60cm)
- 創建
- 不詳 元禄4年(1691)再興
- 開基
- 不詳
- 所在地
- 静岡県掛川市岩滑1273
- TEL
- 0537-74-3415(管理者 掛川市岩滑3278-1 加藤勝司)
- 開帳
- 33年毎(平成5年9月24日開帳)
■御詠歌
「
■菊水寺 縁起
昔、岩滑村に堂塔を並べた古刹があったが、戦国時代、戦乱に巻き込まれ、地蔵堂と観音堂を残してすべて灰になってしまった。その後、寛文12年(1672)10月大洪水に襲われ、観音堂は御本尊ともども失われてしまった。しかし、御本尊はその後、村内の山ぎわで発見され、元禄4年(1691)、村の真言宗修験道繁昌院中島家先祖が自宅内に堂宇を建て、これを祀ったと言われている。これが菊水寺の始まりである。
本尊の千手千眼観世音菩薩は、いわゆる六観音のひとつであり、両眼両手のほかに、左右十手を具し、その中に一眼ずつを有するという姿をしている。
第三十二番 如意輪山 今瀧寺
- 宗派
- 真言宗
- ご本尊
- 如意輪観世音菩薩(木造・座像・30cm・天平元年(729)、行基作の一刀三礼の秘仏)
- 創建
- 天平元年(729)
- 開基
- 行基(聖武天皇の勅願)
- 所在地
- 静岡県掛川市今瀧213
- TEL
- 0537-74-5339
- 開帳
- 60年毎
■御詠歌
「
■今瀧寺 縁起
天平元年聖武天皇勅願、行基による創建という古刹にふさわしい広い境内を有している。山門はいぬ槙の大樹の枝葉を刈り込んで作られたみごとな造形美で必見(市指定重文)。
本寺は真言密教の道場として繁栄し、多くの信者を集めてきた。しかし、戦国時代に入り、武田、徳川の、高天神城を巡る攻防の際に戦火を受けて、堂宇伽藍、文化財、記録などすべてを焼失した。
元和8年(1622)当時の人々により再興。戦火で人材を失うことのなきよう、安産を祈願、祈願布を筒にし、祈願成就の折には底を縫ってお礼参りをする習慣が生まれ、今日に続いている。
本寺には高齢者の為の観音が祀られていて近隣の信仰を集めている。
第三十三番 佐束山 岩井寺
- 宗派
- 真言宗
- ご本尊
- 聖観世音菩薩(木造・立像・行基作)
- 創建
- 天平13年(741)
- 開基
- 行基(聖武天皇の勅願寺)
- 所在地
- 静岡県掛川市岩井寺32
- TEL
- 0537-22-5213
- 開帳
- 33年毎
■御詠歌
「山高き峰のいおりに住む人は 雲にはつせの風やまつらん」
「慈悲の目ににくしと思う人はなし 罪あるものはなおもあわれむ」
「巡礼をみなひとごとにするならば いづく地獄という月のかげ」
「いままでは親とたのみしおいづるを ぬぎやおさむる岩の井の寺」
■岩井寺 縁起
第45代聖武天皇の命によって、新仏三体を持って都を後にした行基上人は、この地に入って不思議な霊力を感じた。そこでこの地を仏法守護の霊山として、本尊救世大悲の像を安置した。時に天平13年(741)正月。
弘仁の頃(810〜24)、空海が行脚、真言密教の道場としてここに国家安穏仏法興隆のために金剛頂経(真言宗の根本経典)一巻を奉納。
足利尊氏(1305〜58)は、圓教僧都を中興の開山としてここを、九谷山平林寺と改め、また、応永9年(1402)足利義満の時、佐束山岩井寺と改めた。
永禄〜天正年間(1558〜92)、甲州武田軍の度々の乱入により七堂伽藍の全てを焼失した。まことに残念なことである。
慶長年間(1596〜1615)、横須賀城主大須賀康高が当山に帰依、現在の伽藍の一部を寄進したものと伝えられている。